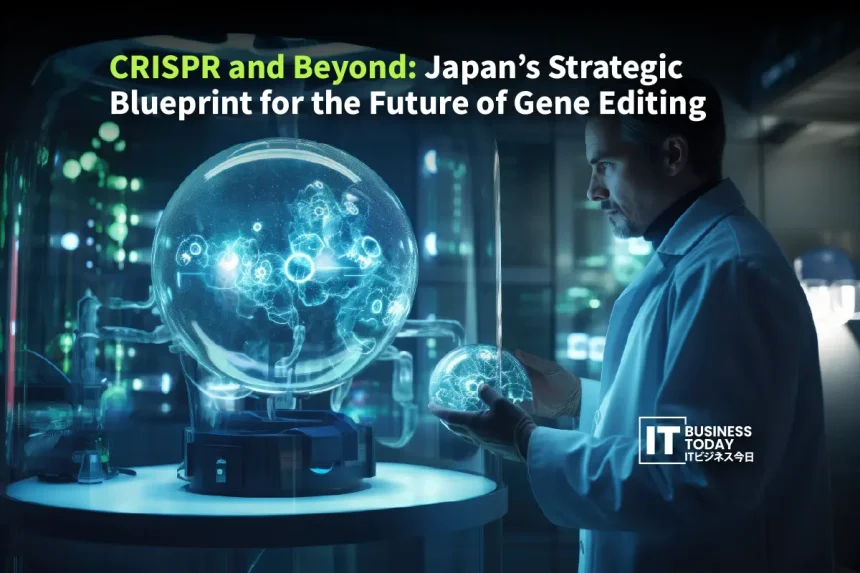遺伝子編集は、もはや実験室の片隅にあるものではありません。日本にとって、遺伝子編集は経済競争力の柱となったのです。CRISPRをニッチな科学として扱うビジネスリーダーは、今後10年間で最も決定的な成長エンジンのひとつとなるものを見逃してしまう危険性があります。
遺伝子コードを書き換えることができる精密なツールであるCRISPRは、すでに世界中で医療、食品システム、工業生産に変革をもたらしつつあります。日本では、CRISPRは国家の野心に直結しています。政府の「バイオエコノミー戦略」は、「2030年までに最先端のバイオエコノミー社会になる」という大胆な目標を掲げています。これは単なる美辞麗句ではありません。日本は、バイオエコノミー市場の拡大を次のように目標としています。 100兆円 バイオテクノロジーを将来の繁栄の原動力とするため。
これは科学のための科学ではありません。新しい産業、新しい市場、そして世界経済における日本の地位を形成することなのです。
日本独自の遺伝子編集エコシステムで基礎固め
日本はライフサイエンスの分野でつまずいたわけではありません。他の国々がバイオテクノロジーをニッチ分野のように扱う中、日本は何十年にもわたり、ひっそりとレンガを積み上げてきたのです。幹細胞研究から製薬のブレークスルーに至るまで、その歴史は重要です。
見る 理化学研究所 バイオリソースリサーチセンター。ここはただの研究所ではありません。CRISPR-Cas9ツールを提供し、アジア最大級のバイオメディカルリポジトリを運営する、国の中枢機関なのです。平たく言えば、もしあなたがここで遺伝子編集の本格的な研究をしているなら、おそらく理研を経由したものに触れているはずです。このようなオープンなリソースのパイプラインは、研究を企業が実際に利用できるものに変えるものであり、棚上げされる科学と市場を再構築する科学との違いなのです。
こちらもお読みください: 日本のEVエコシステム2.0:充電ステーションを越えて
それからPMDA。ほとんどの規制当局はボトルネックとして描かれていますが、日本の規制当局は逆に動いています。レギュラトリーサイエンスと国際的な提携における彼らの仕事は、実際に計画できるルールを作り出します。最高経営責任者(CEO)にとって、この予測可能性は金です。つまり、研究開発費がお役所仕事に溺れることなく、収益につながる可能性があるということです。
そして、資金はすでに流れています。2024年度の民間設備投資額は104.8兆円で、1983年以来の高水準。このような数字は嘘ではありません。日本企業はゲームに身を投じ、海外勢がリードするのを待つのではなく、次の展開に大きく賭けているのです。
それをすべて足し合わせると、着実で、十分な資金があり、商業的に貪欲なエコシステムができあがります。イノベーションを生み出すだけでなく、それを拡大するように設計されたシステムなのです。だからこそ、世界のリーダーたちがバイオテクノロジーについて語るとき、日本は脇役としてではなく、青写真として語られるのです。日本はその青写真なのです。
コア投資
ここからが本題です。遺伝子編集は、研究室で眠っている研究論文ではありません。遺伝子編集はすでに、日本企業にとって重要な市場を切り拓いているのです。そして、もしあなたがC-suiteにいるのなら、これは科学の話ではなく、市場参入の話なのです。
ヘルスケアと医薬品
日本の高齢化はもはや人口動態のトレンドではありません。ビジネスの原動力なのです。個別化医療や再生医療は贅沢品ではなく、国民の3人に1人が高齢者となる日本にとって、生き残るための手段なのです。 65 2035年までに医薬品医療機器総合機構は、遺伝子治療と細胞治療に関する明確なルールを構築し、枠組みを更新し、世界の規制当局と連携しています。それが重要なのは、不確実性を減らすためです。新しい治療法が開発されるとき、規制当局がそれを許可するかどうかを推測したくはないでしょう。その道筋が予測可能であることが望ましいのです。日本の製薬会社にとって、この予測可能性は燃料です。つまり、研究開発に何十億ドルも注ぎ込めば、より早く市場に投入できる可能性があるということです。世界的な投資家にとっては、日本が先進ヘルスケアの発射台となることを真剣に考えている証拠です。
農業と食料安全保障

食料の半分以上を輸入している日本の弱点。遺伝子編集は逃げ道を提供します。政府のバイオエコノミー 戦略 は、2030年に向けた柱のひとつとして、持続可能な一次生産を明記しています。これは、政策的な誇張ではなく、遺伝子編集作物が日本の自給率を高め、気候変動により強くするための最前線の役割を果たすというシグナルなのです。異常気象に耐える作物の開発から栄養成分の強化まで、遺伝子編集は食糧不安を根本から断ち切る可能性を秘めています。食品および アグリテックこれは効率性だけでなく、国家的な妥当性の問題なのです。
産業バイオテクノロジーとESG

ヘルスケアや食品が注目されていますが、産業バイオテクノロジーは静かな革命が起こる場所かもしれません。微生物、酵素、遺伝子編集システムなどを使って、石油を原料とする製造業を持続可能なプロセスに置き換える「ホワイトバイオテクノロジー」。バイオエコノミー戦略では、5年間で30兆円、官民合わせて120兆円の研究開発費を目標としています。この数字は学術的なものではなく、企業の酸素なのです。ESGへのコミットメントと株主からのプレッシャーのバランスをとる経営陣にとって、遺伝子編集と持続可能性が交差するのはここなのです。コスト削減、環境に優しいサプライチェーン、そして国際競争力。
これら3つの領域を合わせると、遺伝子編集は科学的な賭けではなく、市場にとって必然的なものとなります。リーダーにとっての問題は、遺伝子編集が産業を再編成するかどうかではありません。自社がその波に乗るのか、それとも他社が市場を席巻するのを見守るのか、ということです。
規制、倫理、社会的信頼
信頼なきイノベーションは崩壊します。日本はこのことを知っています。だからこそ日本は、規制を障害物としてではなく、進歩を現実のものにする枠組みとして扱っているのです。
カルタヘナ法はそのわかりやすい例です。医薬品医療機器総合機構が管理するこの法律は、遺伝子編集生物の取り扱いに関するルールを定めています。研究所や企業は、前進する前に予測可能なチェックリストを入手します。これはお役所仕事ではありません。市民や投資家を安心させるためのリスク管理なのです。安全対策が講じられていることを知れば、人々は科学を受け入れようとします。
そして、日本は単独でこれをやっているわけではありません。PMDAは細胞治療や遺伝子治療に関する国際シンポジウムに定期的に参加しています。このような対話は、日本が車輪の再発明をしていないことを意味します。その代わり、自国で承認された治療法が海外で壁にぶつからないよう、グローバルなベンチマークに沿った取り組みを行っています。ビジネスリーダーにとっては、将来の摩擦を減らすことができます。国民にとっては、安全基準が密室で水増しされていないことを示すことができます。
倫理的な懸念が消えることはありません。長期的な影響や遺伝的公平性、あるいは意図しない結果についての疑問は残るでしょう。しかし、ここが違います。日本はこうした懸念に早期に、オープンに、明確なプロセスで対処しています。そのオープンさが競争上の優位性になるのです。ここでの信頼はPRではありません。バイオエコノミーのスケールアップを可能にするライセンスなのです。それがなければ、あらゆるブレークスルーはスタートラインで失速してしまうでしょう。
日本がリーダーになる理由
日本は遅まきながらバイオエコノミー・レースに参入したわけではありません。何十年にもわたって軌道を敷き、そして今、そのピースが揃いつつあるのです。政府の政策が安定をもたらし、理化学研究所のような研究機関が研究力を提供し、文化そのものが社会的課題の解決策としてのテクノロジーにオープンであること。このような組み合わせは稀であり、重要なことなのです。
理研のモデルは良い例です。バイオ研究のリソースを産業界や大学に循環させるハブとして機能することで、知識がサイロに閉じ込められるのを防いでいます。企業はゼロから始める必要はありません。実績のあるリソースに接続し、コストを削減し、研究室から市場への道のりを加速することができます。こうして、研究が実際のビジネスにつながるのです。
規制当局も乗り出しています。その PMDAワシントンD.C.の新オフィスでは、日本を目指す外国企業のために無料相談を実施。この一挙手一投足は2つのことを物語っています。第一に、日本は国際的なバイオハブを本気で目指しているということ。第二に、日本がグローバル資本とパートナーシップを流入させるための障壁を低くしていること。投資家はこのようなシグナルに注目します。
企業にとって、遺伝子編集はもはや単なる実験道具ではありません。遺伝子編集は、個別化医療サービスから気候変動に強い農業に至るまで、まったく新しいビジネスモデルのテコとなります。遺伝子編集は新たな市場を生み出し、企業が知的財産と規模の拡大を競い合うM&Aの引き金にもなり得ます。
優位性は明らかです。他国が方向性を議論する中、日本は科学、政策、ビジネスがすでに協調するエコシステムを構築しています。これは競合他社が太刀打ちできない基盤です。
エンドノート
日本にはすでに、他国がまだ探し求めているピースがあります。明確な目標を掲げた政府の戦略、理研を中心とした研究ネットワーク、麻痺させるのではなく現実的な規制当局。これに、テクノロジーを現実の社会問題を解決するための手段とみなす文化が加われば、進むべき道は見えてきます。
しかし、見えることと避けられないことは同じではありません。チャンスは大きく、躊躇するリスクも大きい。世界の競合他社は立ち止まってはいません。市場は日本の決断を待ってはくれません。
今こそ、リーダーがギアをシフトしなければならない瞬間です。CRISPRをはじめとする遺伝子編集ツールは、もはや「有望な科学」の範疇には収まりません。CRISPRをはじめとする遺伝子編集ツールは、もはや「有望な科学」の範疇には収まらないのです。観測の時間は終わりました。次に何が起こるかは、果断な投資と大胆な実行にかかっています。.