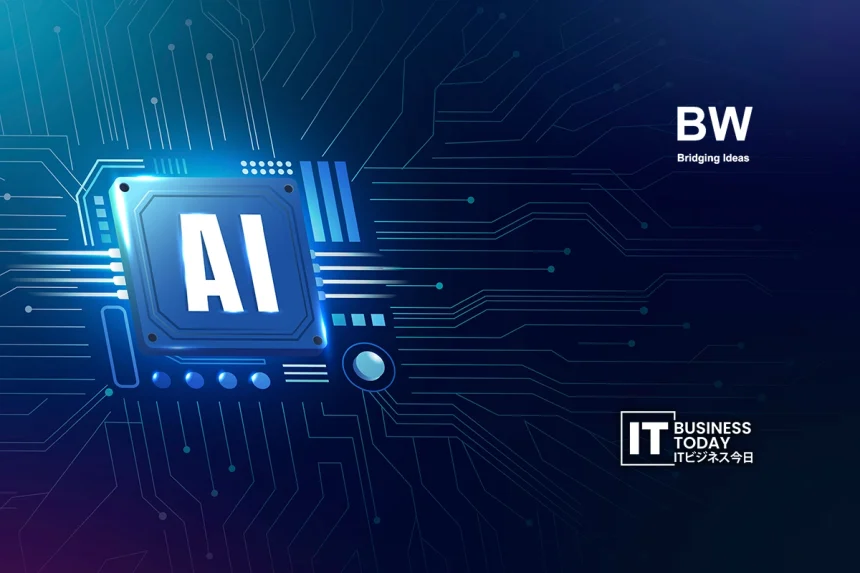ブリッジウェル 株式会社トイトークは、AIキャラクターとリアルタイムで音声会話が楽しめるAIプラットフォーム「ToyTalk(トイトーク)」https://toytalk.ai/ のβ版を2025年8月8日にリリースしました。これまで、専門分野のAIキャラクターを作成するには、ITエンジニアによる高度なチューニングが必要でした。しかし、ToyTalkの特徴は、音声AIに求められる “振る舞い ”と “特定の知識(最大3,000文字)”を組み合わせることで、誰でも簡単に無限のユニークなキャラクターを作成できることです。“
トイトークでは、占い師やおしゃべり、日常生活に役立つアシスタントなど、さまざまなAIキャラクターを選んで会話することができます。また、歴史上の人物(※著作権が消滅している人物に限る)を作成し、当時の様子を聞いたり、こんなことがあったかもしれないと楽しく会話することもできます。また、「独自の知識」欄にQ&Aの内容を入力すれば、Q&Aチャットボットとしても簡単に利用できます。.
トイトークの音声AIは、まるで人間と会話しているかのようにスムーズに会話をすることができます。一般的に人間は0.2秒で応答すると言われていますが、ToyTalkはわずか0.3秒で応答・会話するため、ユーザーは違和感なく人間と会話しているような感覚で会話を楽しむことができます。.
こちらもお読みください: Arent Inc、ソフトウェアのAI統合計画を発表
日常生活におけるAIの活用
OpenAIが提供するChat GPTなど、AIブームと呼べる社会現象が起きていますが、日本での利用率は海外に比べて低く、利用している人でも業務用途に限定されていることがほとんどです。(※ジェネレーティブAIの1日の利用率は、グローバルでは72%ですが、日本では51%と低いです。出典「AI at Work 2025:Momentum Builds, But Gaps Remain“)
トイトークは、生成AIを無料で提供することで、より多くの人に日常生活に役立つツールとして使ってもらいたいと考えています。生成AIは会話音声で利用できるため、タイピングに不慣れな人でも、手がふさがっているときでも利用できます。
AIの技術的メカニズム
AIはコーディングや文章作成、画像生成など幅広い用途で活用されていますが、特定の分野に特化したAIとなると、長期的な学習や高度なチューニングが必要となり、導入が難しくなります。
AIに思い通りに動いてもらうには、それなりのコツが必要です。しかし、多くの人がAIを使わないのは、使い方がわからない、何をすればいいのかわからないからです(※AIを使わない理由の大半は、“使い方がわからない”、“自分の生活には必要ない(何をすればいいのかわからない)”)。出典総務省「情報通信白書」)。このハードルを下げることで、AIの活用が進む可能性があります。.
トイトークは、誰でも簡単にAIキャラクターに指示(ビヘイビア)を出すことができ、AIが自転車の補助輪のようにアシストしてくれるように設計されています。トイトークのいいところは、ITが苦手な人でもマニュアルなしで使えること。.
ソース PRタイムズ